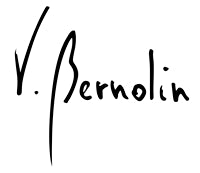リコーダーの分類方法に関して

共有
誰もが体験したことがあるように、楽器を通じた体験を言葉で表現することは非常に難しいです。感覚は感じた感情に密接に絡んでいますが、客観性には絶望的なほど欠けています。この記事では、リコーダーの音色と反応のさまざまな側面を、感覚だけでなく、私の製作家としての経験や、私が聞いたことと関連付けることができた物理的要素をもとに説明しようと思います。物理的要素とは、ウィンドウェイの形状や幅、出口の面取りのサイズと角度、ラビュームの厚さ、ラビュームの窓内での相対的な位置等、楽器の調整に寄与する、測定可能な具体的な要素を指します。このアプローチのメリットは、欠如することによって演奏が困難になる要素とそうでないものを区別できるようになることです。そのため、読者には読み進めるにあたって、寛容的であることを望みます。私が言及する要素は、私の想像や主観的な認識から生じたものではなく、特定の物理的パラメータと関連しているため、この分析には一定の正当性があることをご理解頂けますと、幸いです。
柔軟性 / 抵抗性の関係性:
音色とピッチの変動可能性に関連し、リコーダーに入る空気の圧力によって調整されます。ここでの「抵抗性」は安定性の同義語として使われています。柔軟なリコーダーは、圧力によって音色が変化しますが、抵抗のあるリコーダーは、より安定して変化を吸収し、緩和します。抵抗の非常にあるリコーダーは、固定された音で音楽的な意図を制限することがありますが、あまりにも柔軟な調整は、動きすぎて不安定になり、求められる表現力がピッチと互換性がなくなる可能性があります。より安定した調整は、さらにより強固な低音を可能にします。
倍音
楽器の音色に関して最も理解されていない側面の一つであることは間違いありませんが、定義するのが最も難しいのも事実です。最も興味深い楽器は、しばしば誤って倍音が豊かであると形容されます。しかし、この豊かさは物理学と音響学において、騒がしい楽器、平凡でありふれた音色、魅力のない音色に明確に関連付けられています。むしろ、特定の倍音の発生を制御することが、求められる音色を得るために必要であり、それは偶然の産物ではありません。私は、一部の音楽家たちのみならず、楽器製作者たちさえもこれに関して注意を払わないことに驚かされています。そのため、これはこの研究の中で最も主観的な要素には違いありませんが、私としては妥協を受け入れることはできません。
アタック
楽器の反応性はアタックの速度によって定義されます。柔軟性同様、この要素も慎重に考慮され、調整されるべきです。反応性が高すぎるとリコーダーは繊細で個性的になりすぎますが、アタックが遅すぎると奏者に過剰なエネルギーを要求し、慣性を感じさせます。
オープニング
音色の精度と純度を定義することは、特に70年代と80年代にFred Morganのリコーダーで追求されました。それ以来、よりオープンなリコーダーは、より柔らかい音色を持ち、明るさが少なく、より温かみがあり、二次的な音域は鋭く攻撃的ではないことがわかりました。これは、2000年代以降、Dorothée Oberlinger、 Erik Bosgraafや Maurice Stegerなどの新世代のリコーダー奏者によって示された方向性です。このタイプの調整は、より多くの空気の流れを必要とし、過度にオープンなリコーダーは演奏が難しい場合があります。だからこそ、ここでも妥協が必要です。
トランジェント
アタックは音響的には「トランジエント」と呼ばれ、特に特定のオルガンのパイプやルネサンスリコーダーで聞かれます。顕著なトランジエントは、それがもたらす打楽器的でリズミカルな側面によって、確かなダイナミズムを提供します。その一方で、この様なアタックは、バロック音楽、特にヴィヴァルディの協奏曲にしばしば見られる非常に速いフレーズや連続を妨げる可能性があります。だからこそ、私は目立ったアタックをルネサンスリコーダーやフォーク音楽に限定し、より明確な演奏の必要性があるバロック楽器に関しては、より控えめなトランジエントを好みます。
図:
以下に、私が先ほど述べた要素を要約した図を示します。各ポイントの両極端を対比させて、主旨をより明確に示しています。この図は、私がその影響範囲に照らして配置する各パラメータの影響を特徴づけるのに役立ちます。ただし、これは楽器の特徴を可視化するものではないことは、後段よりご確認頂けます。

以下に、各楽器に関してこれまで言及された要素に関して、0から5の評価を与えた図を掲載します。0から5の意味に関しては、少々議論の余地があるかも知れません。特にトランジェントに関しては、5というのは必ずしも最良とは言い切れません。ただし、ここに示す図は、どの様な調整が必要になるかを視覚的に、わかりやすくとらえられるというメリットがあります。この後ご覧頂く通り、この図式によって、楽器間の比較が大いに容易になっています。
オープンまたはフレキシブルなリコーダー:Ernst Meyer、Fred Morgan
1970年代と1980年代に、前述のように、Fred Morganは、あまりオープンでない調整、純粋で正確な音色、音の柔軟性としなやかさ、非常に速くて扱いやすい高音、そしてあまり力強くない低音域を好むことが多くなりました。

反対に2000年代には、Ernst Meyerがリコーダー奏者に対して非常にオープンな調整を提案しました。より温かく柔らかい音色、強力で非常に安定した低音を持ち、対照的に非常にエネルギッシュなアタックと大きな空気の速度を必要とする高音域といった特徴を有していました。

ベルノリンのリコーダーはどのような位置にありますか?
抵抗 : 私は、音楽家にある程度の自由を与え、実際に楽器にもある程度の柔軟性を持たせる必要があると考えていますが、特に中音域の飽和の欠如と低音の堅牢性を監視しています。
ハーモニクス: 優雅さは常に指針です。私の目標は、可能である限り、常識を超えた楽器をできるだけ多く生み出すことにあります。
オープニング: 今日行っている調整はかなりオープンですが、人間の肺活量の限界を意識しており、要求される空気の流量は合理的で実現可能な範囲に留めています。
アタック: 私は明らかに、アタックが比較的速い反応的な楽器の方向に進んでいます。これは演奏のしやすさという点で有利だと考えています。その代わりに、低音域やアルトリコーダーの高いド#のような構造的に繊細な音符では、アタック時の空気の速度をコントロールする必要があります。このアプローチがもたらす演奏の快適さと音楽的な可能性に私は確信を持っています。
トランジェント性: ガナッシとファン・エイクにはより顕著に表れていますが、バロックフルートには柔軟性をもっと求めます。いずれにせよ、トランジェント性は演奏家にとって負担になったり、音楽の表現を混乱させたりしてはいけません。